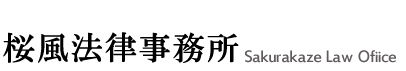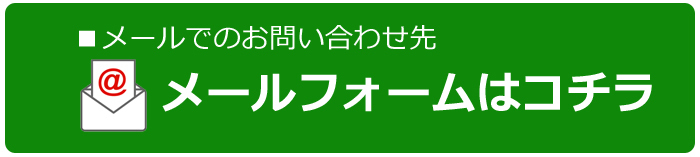後遺障害逸失利益に関する損害賠償請求はお任せください 弁護士窪川亮輔『桜風法律事務所』(西宮)
後遺障害のために、労働する能力や労働する意欲を失ってしまい、災害被害に遭う以前のように働いて、収入を得ることが著しく困難になってしまいます。
そのため、後遺障害が残ってしまった場合には、将来において失ってしまうであろうと判断される将来の収入の補償を求めることができます。
これが後遺障害逸失利益に関する損害賠償です。
桜風法律事務所へご依頼いただいた場合、後遺障害逸失利益が増額する可能性が高くなります
加害者の過失に基づいて後遺障害が残存した場合、被害者は加害者に対して後遺障害逸失利益の賠償を求めることができます。
被害者がご自分で加害者に対して後遺障害逸失利益を請求されることも可能です。
しかしながら、経験上、被害者がご自分で請求された場合に、自賠責基準や労災保険基準で算定された金額を上回る賠償金額を獲得される見込みは低いものと判断されます。
弁護士に後遺障害逸失利益の請求を依頼された方が、多くの後遺障害逸失利益を受け取ることができる傾向が認められます。
これから、被害者がご自身で請求される場合と弁護士に依頼されて請求される場合とで、受け取ることのできる金額にどの程度の差が出るのか、お示ししていきたいと思います。
被害者が自分で請求された場合の金額
加害者側(保険会社や会社など)の意向により変動しますので、被害者がご自身で請求された場合に受け取ることのできる金額を確定的にお伝えすることはできませんが、自賠責保険や労災保険から支払いを受けることのできる金額あるいはそれに近い金額に留まってしまう可能性が高いものと考えます。
■自賠責保険から支払われる後遺障害逸失利益
| 等級 | 自賠責保険から支払われる金額(上限額) |
| 1級 | 1900万円 |
| 2級 | 1632万円 |
| 3級 | 1390万円 |
| 4級 | 1177万円 |
| 5級 | 975万円 |
| 6級 | 798万円 |
| 7級 | 642万円 |
| 8級 | 495万円 |
| 9級 | 371万円 |
| 10級 | 274万円 |
| 11級 | 196万円 |
| 12級 | 131万円 |
| 13級 | 82万円 |
| 14級 | 43万円 |
■労災保険から支払われる後遺障害逸失利益
| 等級 | 労災保険から支払われる金額(障害補償給付) |
| 1級 | 給付基礎日額(以下、省略。)の313日分の年金 |
| 2級 | 277日分の年金 |
| 3級 | 245日分の年金 |
| 4級 | 213日分の年金 |
| 5級 | 184日分の年金 |
| 6級 | 156日分の年金 |
| 7級 | 131日分の年金 |
| 8級 | 503日分の一時金 |
| 9級 | 391日分の一時金 |
| 10級 | 302日分の一時金 |
| 11級 | 223日分の一時金 |
| 12級 | 156日分の一時金 |
| 13級 | 101日分の一時金 |
| 14級 | 56日分の一時金 |
■給付基礎日額とは
業務上又は通勤による負傷や死亡の原因となった事故が発生した日又は医師の診断によって疾病の発生が確定した日(賃金締切日が定められているときは、その日の直前の賃金締切日)の直前3か月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で割った1暦日あたりの賃金額のことをいいます。
労働基準法上の平均賃金を指します。
障害補償給付は原則として基礎給付日額を前提に算定されます。
■特別支給金
労災保険からは、障害補償給付金の他に等級毎に定められた特別支給金が支払われます(特別支給金の具体的な内容や金額につきましては後遺障害等級表でご確認ください。)。
障害補償金は損害賠償金との関係で損益相殺の対象となりますが、特別支給金は損益相殺の対象となりません(つまり、損害賠償金とは別個に支払いを受けることができます。)
裁判基準で算定する後遺障害逸失利益の金額
裁判基準では、以下の算定式を用いて算定した後遺障害逸失利益を算定します。
| 注目 | 後遺障害逸失利益の算定式 |
|---|
基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
■基礎収入額とは
後遺障害が残存しなければ手に入れることができたであろう収入額を指します。
通常、事故発生前1年間の収入額を基礎収入額とします。
■労働能力喪失率とは
後遺障害が残存したことによって失ってしまった労働能力の割合のことを指します。
労働能力喪失率は特段の事情がない限りは労働省労働基準局長通牒(昭32.7.2基発第551号)別表労働能力喪失率表に沿う数値を設定することにしております。
労働省労働基準局長通牒(昭32.7.2基発第551号)別表労働能力喪失率表
| 等級 | 労働能力喪失率 |
| 1級 | 100% |
| 2級 | 100% |
| 3級 | 100% |
| 4級 | 92% |
| 5級 | 79% |
| 6級 | 67% |
| 7級 | 56% |
| 8級 | 45% |
| 9級 | 35% |
| 10級 | 27% |
| 11級 | 20% |
| 12級 | 14% |
| 13級 | 9% |
| 14級 | 5% |
■労働能力喪失期間とは
後遺障害の残存によって収入を失ってしまうであろう期間のことを指します。
未就労者の就労の始期は原則18歳(大学入学を前提とする場合には大学卒業時)、就労の始期は67歳(ただし、症状固定時から67歳までの年数が簡易生命表の平均余命の2分の1よりも短くなる者の労働能力喪失期間は、原則として平均余命の2分の1となります。)。
また、むちうち症の場合は労働能力喪失期間について、12級の場合で10年以内、14級の場合5年以内に制限される判例が多く見られますので、桜風法律事務所でもむちうち症の場合で特段の事情が見当たらない場合に判例にならっています。
被害者がご自分で請求された場合に獲得が見込まれる金額と裁判基準で算定した金額との比較 ~具体的ケースに基づいて
<ケース1>
24歳、給与収入500万円の男子労働者が、交通事故被害に遭い、後遺障害5級が認定されたケースでの比較
■被害者がご自身で解決に努めた場合の獲得金額
被害者がご自身で解決に努めた場合、975万円あるいは同金額に近い金額を獲得できることが予想されます
■裁判所基準で算定される場合の後遺障害逸失利益金額
桜風法律事務所の請求金額はおよそ7020万円となります。
(算定式)
基礎収入額500万円×労働能力喪失率79%×労働喪失期間45年に対応するライプニッツ係数17.7741=7020万7695円
■比較結果
被害者がご自身で解決に努められた場合に獲得が見込まれる金額と裁判基準で算定した金額との間には約7倍程度の金額の差があります。
後遺障害逸失利益の請求は桜風法律事務所にお任せください
桜風法律事務所は、労災事故を原因として後遺障害を抱えられてしまった被害者の損害賠償請求事件の解決に注力いたしております。
■後遺障害等級認定を受けられた方あるいはこれから認定を受ける予定をされている方
■加害者や使用者に過失(落ち度)があると考えられている方
いつでもご相談ください。
加害者や使用者に対して後遺障害逸失利益を請求できる見込みがあるか、
どの程度の後遺障害逸失利益の支払いを受けることができそうか、
お答えいたします。
また、桜風法律事務所では、交通事故、労災事故に関するご相談に関して、初回30分の法律相相談を無料とさせていただいております。
いつでもお問い合わせください。
お電話あるいはメールをお待ちしております。
ご依頼いただいた場合、適切な後遺障害慰謝料の支払いを求めて、加害者や使用者と示談交渉し、あるいは訴訟提起をいたします。