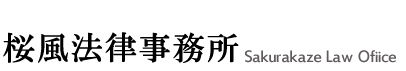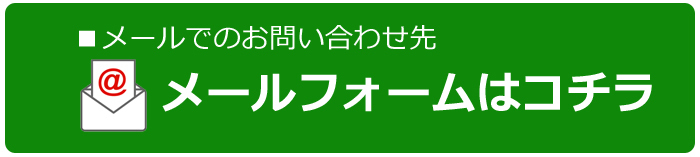| 等 級 | 障害の態様 | 自賠責保険金額 | 労災保険金額 |
| 第1級 | 以下のいずれかの障害が残存している場合に認定される。 ①重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要するもの ②高次脳機能障害による高度の認知症や情意の荒廃があるため、常時監視を要するもの | 4000万円 | ・障害補償年金:給付基礎日額の313日分 ・障害特別支給金:342万円 ・障害特別年金:算定基礎日額の313日分
|
| 第2級 | 以下のいずれかの障害が残存している場合に認定される。 ①重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に随時介護を要するもの ②高次脳機能障害による認知症、情意の障害、幻覚、妄想、頻回の発作性意識障害等のため随時他人による関しを必要とするもの ③重篤な高次脳機能障害のため自宅内の日常動作は一応できるが、一人で外出することなどが困難であり、外出の際には他人の介護を必要とするため、随時他人の介護を必要とするもの | 2590万円 | ・障害補償年金:給付基礎日額の277日分 ・障害特別支給金:320万円 ・障害特別年金:算定基礎日額の277日分 |
| 第3級 | 以下のいずれかの障害が残存する場合に認定される。 ①意思疎通能力、問題解決能力、作業負荷に対する持続力、社会行動能力のいずれか1つ以上の能力が全部失われているもの ②意思疎通能力、問題解決能力、作業負荷に対する持続力、社会行動能力のいずれか2つ以上の能力の大部分が失われているもの | 829万円 | ・障害補償年金:給付基礎日額の245日分 ・障害特別支給金:300万円 ・障害特別年金:算定基礎日額の245日分 |
| 第5級 | 以下のいずれかの障害が残存する場合に認定される。 ①意思疎通能力、問題解決能力、作業負荷に対する持続力・耐久力、社会行動能力のいずれか1つ以上の能力の大部分が失われているもの ②意思疎通能力、問題解決能力、作業負荷に対する持続力、社会行動能力のいずれか2つ以上の能力の半分程度が失われているもの | 1574万円 | ・障害補償年金:給付基礎日額の184日分 ・障害特別支給金:255万円 ・障害特別年金:算定基礎日額の184日分 |
| 第7級 | 意思疎通能力、問題解決能力、作業負荷に対する持続力、社会行動能力のいずれか1つ以上の能力の半分程度が失われているもの | 1051万円 | ・障害補償年金:給付基礎日額の131日分 ・障害特別支給金:159万円 ・障害特別年金:算定基礎日額の131日分 |
|
第9級 | 意思疎通能力、問題解決能力、作業負荷に対する持続力、社会行動能力のいずれか1つ以上の能力が相当程度失われているもの | 616万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の391日分 ・障害特別支給金:50万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の391日分 |
| 第12条 | 意思疎通能力、問題解決能力、作業負荷に対する持続力、社会行動能力のいずれか1つ以上の能力が多少失われているもの | 224万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の156日分 ・特別支給金:20万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の156日分 |
| 第14条 | MRI、CT等による他覚的所見は認められないものの、脳損傷のあることが医学的にみて合理的に推測でき、高次脳機能障害のためわずかな能力喪失が認められるもの | 75万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の56日分 ・障害特別支給金:8万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の56日分 |
等級認定のポイント
等級認定は、①事故による脳損傷の有無、②障害の程度、の2段階に分けて検討されます。
① 脳損傷の有無
脳の器質的損傷には、事故による外力の作用で直接脳が損傷する場合(一次性損傷)と頭蓋内出血等により脳が圧迫されて脳が損傷する場合(二次性損傷)があります。
脳について一次性損傷あるいは二次性損傷が認められることは等級認定を受けるための原則的な要件となります。
ただし、びまん性軸索損傷の場合、事故直後の画像には異常が認められない場合も多くあります。
そこで、びまん性軸索損傷の場合は、事故直後に脳損傷が認められないという事情だけで後遺障害等級が認定されないという結論にはなりません。①一定の期間・一定強度の意識障害が存在し、②画像資料等でびまん性脳室拡大・脳萎縮の所見が認められる場合には、後遺障害等級が認定されております。
② 障害の程度
高次脳機能を、意思疎通能力、問題解決能力、作業負荷に対する持続力、社会行動能力の4つの能力に分類し、それぞれの喪失の程度を検討して、等級認定が行われます。
適切な等級認定を受けるためには、以下の各事項を明らかにするための資料の提出が必要です。
・記憶や認知に関する障害の有無・程度
・具体的な就労・就学状況、日常生活状況
・具体的な場面において生じている生じている支障の内容
■日常生活状況の報告
被害者の、人格や情動の変化、社会的適応性の変化を的確に把握するためには、経過診断書、後遺障害診断書、カルテなどの医学的書類を提出するだけでは足りません。
被害者と日常生活を共にして介護を担当している家族、同じ職場での同僚、同じ学校の同級生や担任教師などから、事故前後における被害者の行動の変化を具体的に聴き取り、資料とすることが必要です。
自賠責保険において主治医の意見書及び家族からの報告書の書式が用意されています。
■神経心理学的検査の留意点
人の心理的機能(意識、注意、知能、言語、記憶、視覚、聴覚など)に関する神経心理学的検査は、高次脳機能障害の内容や程度を判断するにあたって重要な資料とされています。
ただし、以下の各点に留意しておく必要はあります。
・知能指数は正常な範囲であっても高次脳機能障害が残存している例もあること
・認知機能検査(MMSE)で認知症と判断されなくても高次脳機能障害がないとはいえないとされていること
裁判所による脳の器質的損傷の有無の判断に関する一般的な傾向
判例は、画像所見の有無だけでなく、事故直後の意識障害の程度、経時的な画像の比較などから、総合的に脳の器質的損傷の有無を判断しています。
画像所見による異常は認められないものの、事故直後の意識障害の存在から脳の器質的損傷の存在を認定した判例もあります。