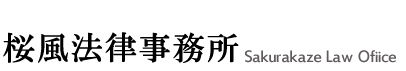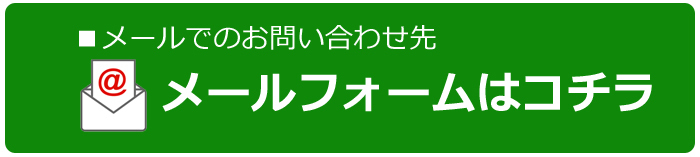後遺障害に関する損害賠償問題への取り組みについて 弁護士 窪川亮輔『桜風法律事務所』大阪・神戸
いくら治療を受けても、治癒にいたらない怪我があります。それが後遺障害です。
後遺障害が残ってしまった場合、加害者は被害者に対して後遺障害に関する損害賠償金を支払うべき義務があります。
さて、後遺障害が残存した場合の損害賠償金を受け取るまでの一般的なプロセスは以下のとおりです。
①医師より後遺障害診断書の作成を受ける。
②自賠責保険調査事務所に対し後遺障害診断書等を提出し、後遺障害等級認定の申立てをする。
③自賠責保険調査事務所による等級認定を受けた後、加害者に対して損害賠償請求を行う。
けれども、どのようなケースでもスムーズに後遺障害残存に関する損害賠償金を受け取ることができません。
それは、自賠責保険調査事務所が適切な等級を認定してくれなかったり、認定された等級自体は適切であっても、加害者側が適切な損害賠償金の支払いを了解しない場合が多くあるからです。
このような場合に、適切な損害賠償金を獲得するために被害者が自分だけで対応することはとても困難です。
当事務所は、後遺障害に関する損害賠償問題についても専門的に取り組んでおります。
以下、当事務所の取り組み方についてご紹介いたします。
適切な後遺障害認定等級を獲得するための取り組みについて
後遺障害の残存に関して損害賠償請求をするにあたってまず行わなければならないことは、自賠責保険調査事務所への等級認定の申立てです。
等級認定の申立てをするには医師による後遺障害診断書の作成が必要となります。
等級毎に認定されるための要素が定まっているところ、後遺障害診断書に所定の事項が記載されていなければ適切な等級認定がされることはありません。
当事務所は等級毎の認定要素をきちんと把握したうえで、後遺障害診断書に認定に必要となる事情がきちんと記載されているかをチェックします。
もし、後遺障害診断書に認定に必要となる事情がきちんと記載されていないのであれば、医師に対して後遺障害診断書の修正もしくは追加の意見書をいただくようにしています。
そのような対処によって初回の後遺障害等級認定の申立てにより適切な等級が認定される可能性が高まります。
後遺障害等級認定申立てによって想定していた等級が認定されるとは限りません。
そのような場合、異議申立てをするか否かを検討します。
異議申立ては、異議を申し立てる旨の書面を提出するだけで、行うことができます。
しかし、ただやみくもに異議を申し立てても、異議は却下されてしまいます。
異議申立てにより認定結果をよりよいものにするためには、自賠責保険保険調査事務所が依頼者の納得のできない認定をした理由を正確に把握して、その理由が誤ったものであると理解してもらうための対策をとる必要があります。
当事務所は、自賠責保険が依頼者の納得のできない認定をした理由を正確に把握できます。
そのうえで、自賠責保険調査事務所に対して誤った認定理由であることを理解してもらうための対応策を検討します。具体的な対応策は依頼者との協議を踏まえて決定します。
納得のできない理由を正確に把握し、適切な対応策を取る、これによって異議申立ての結果よりよい認定結果が得られる可能性が高まります。
異議申立てをもってしても依頼者が納得できる認定結果が得られない場合もあります。
そのような場合でも、訴訟を提起すれば、裁判所は後遺障害の存在を認定し、損害賠償請求を認容する可能性があります。
実際に当事務所が依頼を受けた数多くの案件において、認定結果は非該当ながら後遺障害に対する損害賠償が認容されました。